第2部 シンポジウム
スケジュール/チケット
大人 ¥1,000
学生 ¥500
高校生以下 ¥100
-
03.17(Mon)14:3015:50メディアシップ日報ホール
3/17(mon)14:30-15:50
at 日報ホール
これまでのシンポジウムはテクノロジー、著作権、雇用が議題になっていたと思いますが、NIAFFでは「芸術表現におけるAI・生成AIの役割」というクリエイティブな切り口から、クリエーター側から見た今後の創作に関してを中心に展開します。
登壇者

手塚 眞(ヴィジュアリスト)
1961年東京生まれ。高校時代から映画制作を始め、数々のコンクールで受賞。以後、映画・テレビ等の監督、イベント演出、本の執筆等、創作活動を全般的に行っている。1985年『星くず兄弟の伝説』で商業映画監督デビュー。1995年富士通のPCソフト『TEO~もうひとつの地球』をプロデュース。19か国で50万本のヒットとなる。1999年『白痴』がヴェネチア国際映画祭で上映されデジタル・アワード受賞。2020年『白痴』公開20周年を記念したデジタルリマスター版と手塚治虫原作の『ばるぼら』が全国公開。テレビアニメ『ブラック・ジャック』では2006年東京アニメアワードのテレビ部門優秀作品賞受賞。AIを使って手塚治虫の漫画を描く「TEZUKA2023」プロジェクトでは総合ディレクターを務める。宝塚市立手塚治虫記念館名誉館長など、手塚治虫遺族としても活動している。著作に『父・手塚治虫の素顔』(新潮社)他。
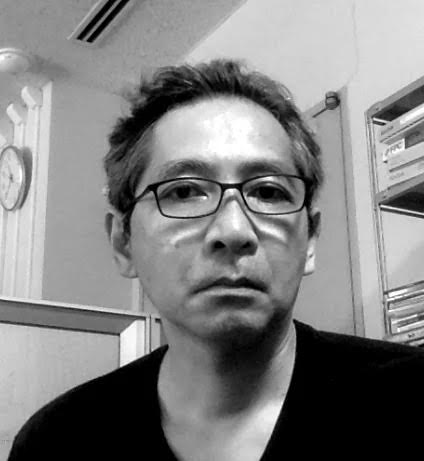
長嶌寛幸(東京芸術大学大学院映像研究科教授)
音楽家、サウンドデザイン・スーパーバイザー。学生時代に石井聰亙(現・岳龍)監督の映画音響ライヴ・リミックスを行ったのをきっかけに、映像作品の音楽、音響を手掛けるようになる。近作は『空に住む』(青山真治監督)、『愛のまなざしを』(万田邦敏監督)、『Chorokbam』(ユン・ソジン監督)、『ザ・ミソジニー』(高橋洋監督)など。また、寺井昌輝らとの電子音楽グループ「Dowser」、ヴォーカリストのPhewとの「106」、詩人の松井茂との「Shinigiwa」での活動も行っており、2022年からは、御茶ノ水 Rittor Baseの5.1.8chのイマーシブ音響空間での「PSYCHO AND ILL HAUS 音像空間劇」にも音楽担当として参加している。2014年より東京藝術大学大学院映像研究科教授。

飯塚直道(株式会社KaKa Creation CCO/プロデューサー)
2016年に株式会社サイバーエージェントに新卒入社。ABEMAにて「にじさんじのくじじゅうじ」(協力:ANYCOLOR株式会社)「P-sports」(協力:株式会社ポケモン)などのゲーム番組プロデューサーを担当。2018年からは株式会社Production I.Gにてアニメの制作現場入りをし、制作進行を経験後、Netflixオリジナル「ULTRAMAN」FINALシーズンや劇場作品「攻殻機動隊 SAC_2045 最後の人間」のラインプロデューサーを担当。KaKa CreationではCCO(チーフ・コンテンツ・オフィサー)として、プロジェクトの企画と品質担保を請け負っている。現在もプロデューサーとして数本のアニメ作品を担当。

中島良(合同会社ズーパーズース代表社員・監督)
映画「なつやすみの巨匠」をはじめ7本の長編映画を監督。
コロナ禍を機に起業し、モーションキャプチャースタジオを開設。
24年映画「 死が美しいなんて誰が言った」がアヌシー国際アニメーション映画祭・プチョン国際ファンタスティック映画祭に入選。同作は生成AIを全編に使用し、賛否両論を巻き起こした。
その後、生成AIを補助ツールとして活用し、実写とアニメの垣根をなくす制作手法の確立に取り組む。現在、AIによる表情コントロールツールやイベント進行ツールなど幅広く映像制作をサポートする開発に着手。

荒牧伸志(SOLA Digital Arts CCO・監督)
1960年生まれ。福岡県出身。岡山大学在学中に手がけた自主制作アニメがきっかけとなり、メカニックデザイナーとして活動を開始。TVアニメ『機甲創世記モスピーダ』(1983〜1984)やOVA『メガゾーン23』シリーズ(1985〜1989)のメカデザインを担当。OVA『メタルスキンパニック MADOX-01』(1988)で監督デビュー。
スケジュール/チケット
大人 ¥1,000
学生 ¥500
高校生以下 ¥100
-
03.17(Mon)14:3015:50メディアシップ日報ホール


